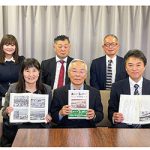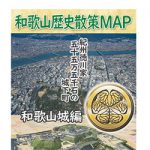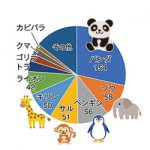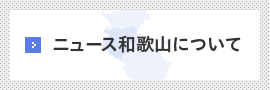舞台役者、舞妓、相撲取りらが髪結いや化粧の下地に今も愛用するびん附け油。製造する企業は全国数社と少なくなる中、和歌山県内で唯一手がけるのが和歌山市宇須の化粧品メーカー、シマムラだ。同社でも職人は和田浩一さん(70)一人となったが、江戸時代から受け継がれてきた技を、昨年入社した山口大貴さん(23)に伝え始めた。和田さんは「創業以来175年間守られてきた技術。若い世代につなぎ、200年目を迎えられるようにしたい」と意気込む。
シマムラの職人 和田浩一さん 江戸期から伝わる技 若手に

直径約40㌢の器に、ハゼを原料とする木蝋(もくろう)と、なたね油を熱で溶かして混ぜた液体を流し込む。冷めて水面の縁が白く固まり始めたころ合いを見て棒で練り始める。溶け残って小さな固まりになる木蝋をつぶしながら、空気を含ませるように練り合わせ、滑らかに仕上げる。「混ぜすぎると、腰がなく柔らかい〝品質が泣いた〟状態になる。気候や湿度で固まる速さが変わる。棒を伝って感じる固さと長年培った勘が頼りです」と和田さん。
同社が作る「紀州びん附け」は天保13年(1842年)の創業当時から販売する看板商品。舞台化粧品を扱う美壽屋(大阪市)の前田美保さん(60)は「90年前の創業時から仕入れています。他社製品に比べ、粘りがあって、化粧持ちが良く、『紀州びん附けでないと』と選んでくれる役者さんや舞妓さんは多い」と絶賛する。
和田さんは23年前、当時常務だった島村辰彦社長(65)から技を引き継いだ。5年前に脳こうそくになり、また、3年前に木蝋業者が廃業し、継承を考え始めた。「別の業者から仕入れた木蝋では思うような仕上がりにならなかった。体力も落ち、もう終わりかと思いました」。良質の木蝋が福岡の業者で見つかり、昨年、入社したばかりの山口さんに技を伝え始めた。
月数回、注文を受けると、2人で工房にこもる。山口さんは和田さんの作業を見て、途中から棒を握る。先端に神経を集中させ、練り始めと練り終わりのタイミングの見極め、棒の返し方や練り加減の感覚を磨く。山口さんは「まんべんなく空気を含ませ、練りすぎないように。シンプルな作業ですが奥深く、要領を得るのには時間がかかりそうです」。和田さんは「私も初めはお客さんから『細かい粒が残っている』『使用感が違う』などの指摘をもらいました。こうしたプレッシャーが成長を後押ししてくれる」と見守る。
明治以降、ちょんまげを結わなくなるなど、ライフスタイルが変化し、びん附け油の需要は低下した。かつて全国各地にあったメーカーは今では数社になり、県内では唯一になった。同社はこうした社会の変化に対応し、大正期に日本初の民間栽培によるオリーブ園を香川県小豆島に開設。事業の主軸は食用油や化粧品になったが、島村社長はびん附け油にこだわる。「昭和初期に職人が1人になりました。しかし、『欲しいという声をいただける限り作り続ける』という社の精神があります。社のルーツである商品を守り、日本文化を支えます」
和田さんは昨年、長年の功績が評価され、厚生労働大臣表彰「卓越した技術者(現代の名工)」に選ばれた。「会社の歴史が受けた賞です」と謙そんし、「数字や文字で表せない技術で、経験が大事。焦らず、じっくり伝えます」と力を込める。山口さんは「全ての工程を1人でこなせるようになるのが目標。役者に『気持ちいい』と言ってもらえるびん附けを作りたい」と意欲をみせている。
写真=棒で練る山口さん(左)と見守る和田さん
(ニュース和歌山/2017年7月15日更新)