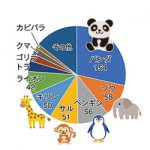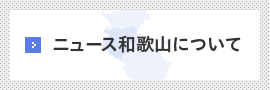有名な女優の息子であるタレントが8月に事件を起こし、テレビや雑誌が大騒ぎしました。親である女優の謝罪会見は一挙一動があげつらわれました。さて、成人した子の不祥事は親の責任なのでしょうか。
1925(大正14)年、成人した子の不祥事で親の責任が問われる事が続きました(有地亨著『日本の親子200年』新潮社)。一人は〝日本細菌学の父〟北里柴三郎博士。31歳の長男が情死事件を起こし、長男だけ生き残ったのです。博士は「一家一門の不名誉」と爵位の返上、貴族院議員、慶応大学医科学長、日本医師会会長の辞職を願ったのです。また同年、長唄界を代表する重鎮の娘が、自らの夫の弟子と不倫をしていたことが発覚しました。重鎮は「今後、公開席上には一切出演せず、謹慎する」と責任をとりました。
東京朝日新聞で、当時、これらについて紙上討論会が行われています。投書を募ると、親に「責任がある」が357通、「責任がない」は330通と少しだけ「ある」が上回りました。
「親の人格のある部分は子に反映する」「個人主義の今日でも私は家長として、親としての責任を糾弾する」。こちらは道徳や家を重んじ、責任を問います。一方は「子が勝手にしたことに責任はない。子は親の付属物ではない」「親は子が成人した以上、厳正なる批判者であり、適切なる忠告者であるべきだが、それ以上であってはならない」。親子は一体でなく、一対一。近代的、個人主義的な考えです。
当時は「新旧道徳の過渡期」と位置づけられていました。しかし、91年たった現在、子が成人すれば親に責任はないとの声が半分はあったでしょうか。
近年、多様な育児書や雑誌が発行され、「こうすればこんな子に育つ」という類の書籍も次々と出ます。また、子どもの貧困という親の経済状況が直に子にはねかえる問題も根が深く、子どものよりよい自立を促すより、「子は親次第」という考え方が強まっていると思えてなりません。親子を一緒に断罪しても、今、疑問の声が起きないのは、それが社会通念化しつつある証ではないでしょうか。
北里博士の辞職願に当時の慶応大学塾長は「家族の罪を自分も負うのは罪三族に及ぶ昔風の考え」と受け付けませんでした。世間の風は私たちがつくり、私たちを左右します。少なくとも大正期にはあった程度の理性は取り戻したいです。(髙垣)
(2016年9月24日号掲載)