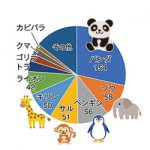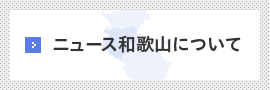車窓から見慣れた天守が見えて来ると、急に懐かしさが湧いてきて、ふるさとに帰ってきた実感を味わうことがあります。
詩人で小説家の佐藤春夫の和歌山城を想う散文詩が『古城にうたう』(鹿島出版会・昭和41年)に載せられています。
「虎伏城には厳然たる天守閣ありて 白壁日にかがやき 故郷への行くさ帰るさに 年久しくふり仰ぎ見て わが母恋ふる料(しろ)なりしを 昭和の兵火海を渡りて降りそそぎ 櫓も天守も焼け落ちたるいと(大変)口惜し」と空襲による焼失を惜しんでいます。
小説家の津本陽も著書『戦国城塞傳』(PHP研究所・平成15年)で「私にとり、もっとも身近な城といえば和歌山城である。(中略)私たちは毎日、天守閣の威厳を仰ぎ見ながら、三年坂と呼ばれる坂道を石垣に沿ってのぼって通学したものだった。(中略)1945年7月9日、わが家のある和歌浦からも、鷺ノ森御坊の方向に巨大な紅蓮の火柱が上がるのが見えたことを、今もはっきり記憶している」と城への想いと空襲で燃え落ちる天守の印象を語っています。
この心境は他の城下に暮らす人も同じだったのでしょう。戦災で失われた天守は、戦後和歌山城に続いて大垣城、名古屋城、熊本城など相次いで再建されていきました。その熊本城は、2016年4月の大地震で甚大な被害があり、天守の灯が丘上から消えました。毎夜、当たり前のように浮かんでいた天守の灯が消えたことで、心が沈み、わが家の被害をおいても天守の灯を願う市民が多かったと言います。空襲で和歌山城天守が虎伏山から消えた時も多くの人が同じ感慨だったようで、1958(昭和33)年の天守再建に多くの寄付が集まったと言います。
かつては、街のどこからでも見えた和歌山城天守ですが、近年建てられたビルなどで、駅舎を出ても望めなくなりました。「ふるさと和歌山城」を望める範囲は狭まったかも知れませんが、虎伏山の天守を中心に、麓の大手門や水堀、そして二ノ丸や砂ノ丸などをビルの窓から楽しめるようになりました。
写真=真砂丁から見た天守群
(ニュース和歌山/2019年2月16日更新)