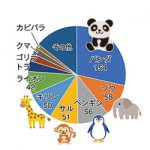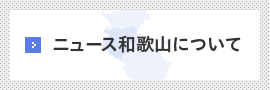講座「死と向き合い、生を考える集い」が1月23日、和歌山市西高松の松下会館で開かれ、約180人が自身や家族の最期について考えた。企画した粉河高校定時制の児玉恵美子教頭は「団塊世代を中心にリアルな問題として感じているようでした。避けられがちな話題ですが、日常的に語り合える場が広がれば、終末期を温かく迎えられる地域になるはず」と話していた。
がん経験者や緩和ケア医師らを講師に、死を意識し人生を大切にしてもらうため、和歌山大学地域連携・生涯学習センターの研修員だった児玉さんが2003年に始めた講座。今年は紀の川市で多くの在宅患者を看取ってきた坂口健太郎医師とケアマネジャーがオリジナル演劇に挑み、親の看取る場をめぐり意見が割れる家族を描いた。
自宅で最期を迎えたい父の意向を叶えようとする家族と、病院での延命治療を望む家族…。参加者は鑑賞後、パートナーや親を亡くした経験、最期の迎え方について世代間でどのように語り合うかなど意見を交換した。坂口医師は「どのように親を看取るかで、自分の死に方が決まる。次に看取られる世代は、子どもへの最後の授業として死に方を考えてほしい」と訴えた。
参加した黒瀬修さんは「死期が迫った認知症の親を自宅へ連れて帰り、好きな物を食べさせてあげた経験を話しました。やはり、身体のケアより、心のケアが大切だと思いました」、辻隆士さんは「役者さんの熱演に心打たれました。生き様と共に死に様についても元気な内に決めておいて、身近な人に言葉で伝えておくことが重要ですね」と語っていた。
写真=ケアマネジャーが演劇に挑戦した
(ニュース和歌山2016年1月30日号掲載)