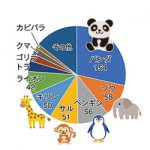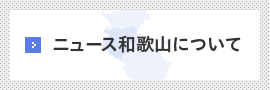今夏、全国高校野球選手権大会が100回の節目を迎える。和歌山県勢の夏7度の優勝は全国3位。戦前の和歌山中、海草中をはじめ、戦後は公立で唯一春夏連覇を達成した箕島、平成に一時代を築いた智辯和歌山と、野球王国の流れが脈々と続く。甲子園最多勝を更新中の智辯和歌山監督、髙嶋仁さん(71)と、全盛期の箕島をつくった故・尾藤公(ただし)元監督の長男で現監督の強さん(48)が、甲子園への思いを熱く語る。(敬称略)
――高校時代、甲子園とのかかわりは。
髙嶋 長崎・海星の2年だった1963年と翌年、夏の大会に出場しました。大きなグラウンドに観客がいっぱい。入場行進で足がふるえるほど感動したことは今も覚えています。この時、「指導者として甲子園に来る」と決めました。
尾藤 選手では出ていません。小中学生のころは連覇もあり、箕島が最も強かった時代。「甲子園は行けるもんや」という感覚で、「レギュラーを取れるか」が問題でした。なめてたんですね。
――指導者として立った聖地は。
髙嶋 70年から10年間、奈良の智辯学園で指導し、春夏3回出場しました。和歌山に来たのは創部2年目の80年。チームは同好会的で、甲子園が目標の私とは開きが大きかった。前年、春夏連覇した箕島を目標に猛練習し、85年の選抜で初出場しました。2年後から夏に隔年で出ましたが、初戦敗退が続きました。
尾藤 監督になった2013年、いきなり夏に出た時は、「待ってたよ」と温かく迎えられました。父が率いた箕島が甲子園で大活躍したことを知っている人たちからの言葉。うれしい反面、「こんなこと言われてるうちはアカン」と思いました。
――出場で学んだのは。
髙嶋 出て初めて分かることがあります。5回目の甲子園となった92年夏、ネット裏のお客さんに「また負けに来たんか」と言われました。ビデオを見直すと、どれも勝てた試合でした。これまで〝出る練習〟はしてきたものの、〝勝つ練習〟はしていなかったと痛感しました。そこから甲子園で優勝する方法を考えました。投手を複数育て、甲子園決勝から逆算し、和歌山大会を見据える。決勝でエースが投げるために、それまでだれが投げるかを決めます。ですから、県大会1回戦でエースが投げずに負けることがありました。
尾藤 甲子園で試合をして、この試合に勝つか負けるかより、優勝するのはとてつもなく大変と分かりました。たまたまでは優勝できない。初めて「野球をするのが怖い」と感じました。
髙嶋 私の人生そのもの
尾藤 優しさ、厳しさある場
――おふたりにとって甲子園とは。
髙嶋 人生そのもの。甲子園に出るために指導者になり、ずっとやってきました。何回行っても選手が違うから新鮮です。何より、監督の私が一番望んでます。戻って1週間もすると「また行きたい」と禁断症状が出るほど魅力的です。
尾藤 父は「甲子園って、母親のような優しさと、父親のような厳しさを持ち合わせている」とよく言ってました。何度も出場し、いろいろなことを経験したいですね。
――100回大会を機に目指すのは。
髙嶋 甲子園で初めて優勝したころ、箕島の現役監督だった公さんから「自分のチームのことだけでなく、和歌山の若い指導者を育てるのもあんたの仕事」と言われました。ただ、私はまだまだ甲子園に行きたい。他校の監督に経験を伝え育てるのは、監督を辞めてからです。
尾藤 失礼ながら、智辯は以前ほど甲子園で上位に行けないことが増えました。それは智辯に何連覇も許してきた和歌山のレベルの低さが原因です。髙嶋監督にはさらに高い域に行ってもらい、その智辯を倒すためにどうするか。各チームが真剣に考えれば、県全体がレベルアップし、強い和歌山の復活につながると思います。
写真上=「野球の怖さを知りました」と話す尾藤監督、同下=「何回行っても新鮮な場所です」と目を輝かせる高嶋監督
(ニュース和歌山/2018年1月1日更新)