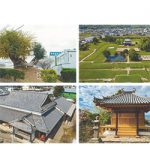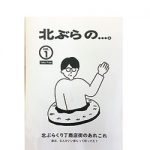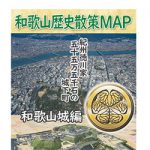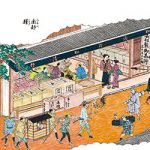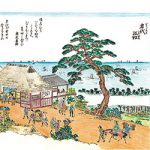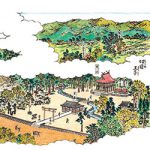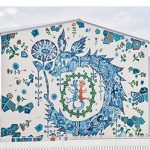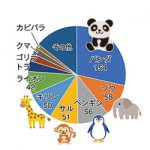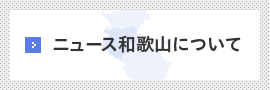不安和らげ 落ち着きに期待
認知症の人が手を入れて使う筒状のニット小物「認知症マフ」。外側と中に縫い付けられた毛糸のボールなど柔らかなアクセサリーを触ることで不安が和らぎ、落ち着きやすくなるといわれている。介護施設にマフを進呈するボランティアグループと、医療現場で生かそうとする病院の取り組みを見た。
貴志川のグループ 制作が生きがいに
認知症マフ作りのボランティアグループを昨年5月に立ち上げたのは、紀の川市貴志川町の貴志川生涯学習センター公民館主事の野口八江さん。一人暮らしの母親の「何もやる気が起きない」というつぶやきが始まりだった。
「母の生活の張りになるものを」と探すうち、毛糸で作る認知症マフを知った。早速、和歌山市の制作グループを訪ねたところ、手芸が得意な母親は目を輝かせて「やってみる」。完成させた一枚目が、能登半島地震の被災地へ贈られ、喜ばれたと聞き、「役に立つことが出来た」と笑顔を取り戻した。
母親の変化を間近で見ていた野口さんは、「高齢者の生きがいになる」と直感。紀の川市で50年以上、編み物を指導する木下美津子さんに協力を依頼した。認知症マフを初めて知った木下さんだったが、申し出を快諾。同市社会福祉協議会の声かけで集まった15人が月1回、同センターで制作に励み、住民や介護施設などに進呈している。
貴志川町の介護老人保健施設みくるまは昨年9月、マフ20枚と人形20体を受け取った。ふんわりと温かく、柔らかな飾りのついたマフは利用者に好評で、手を入れて使うだけでなく、体の下に敷いて寝たり、互いに見せ合っておしゃべりに花を咲かせたり。自分の部屋に戻るのが難しい人は、人形を入口に置き、目印にしている。ケア長の小守幸さんは、「治療の管を装着しているときも、マフがあると気持ちがそちらに向くのか、落ち着いているように感じます」。手先を使うことの効果にも注目しており、「いつか利用者とボランティアの皆さんで一緒に作れたらいいですね」と描いている。
済生会和歌山病院 毛糸提供 協力募る
和歌山市十二番丁の済生会和歌山病院では昨秋から、認知症マフ作りに取り組み始めた。
認知症患者は点滴やチューブ類を外すことが多く、従来から、生命に関わる治療の場合はやむを得ず、ミトンやベルトで身体拘束することがあった。看護師で副院長の廣瀬朱実さんは、「私たちも罪悪感があって。いつも『ごめんよ、ごめんよ』と言ってるんです」と苦しい胸の内を明かす。現場のジレンマを話し合う中で、マフが話題に上り、現状を変える一歩になるかもと導入を決めた。
ただ、看護師や職員が仕事の合間に編んでも、なかなか目標の50枚までそろわず、家族の手伝いを含めても約20枚ほどにとどまる。そこで、制作してくれる人を募ろうと、マフの紹介ポスターを外来患者の目につきやすい場所に掲示し、ホームページでも発信を始めた。また、趣旨に賛同した手芸店、同市新中通のクボイトと駿河町のサンドウから毛糸の寄贈を受け、制作者に提供する体制を整えた。
副看護部長の櫻井恵理さんは、「まとまった数が用意できれば、患者さんにどんないい影響があるか見通せるようになる。マフが認知症の理解につながればうれしい」と期待する。廣瀬さんは、「不安が和らいでスムーズに介助できるようになれば、看護師の心にも余裕が生まれ、寄り添った対応ができる」と考えている。
いずれも協力者を募集中。貴志川町生涯学習センター(0736・64・2273)、済生会和歌山病院(073・424・5185)。
(ニュース和歌山/2025年4月5日更新)